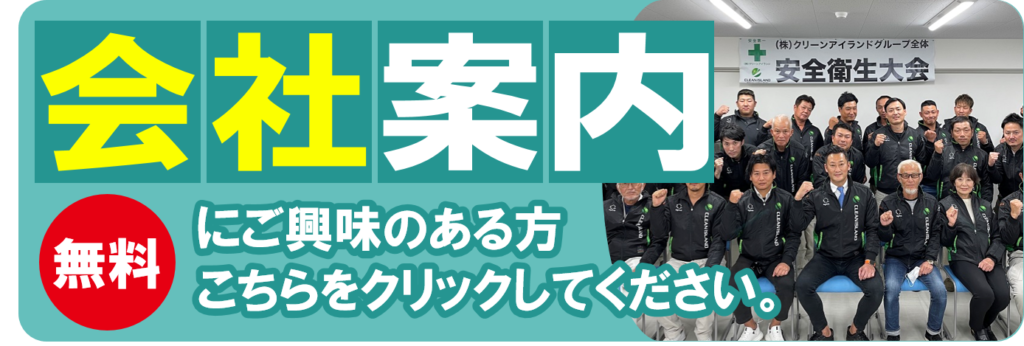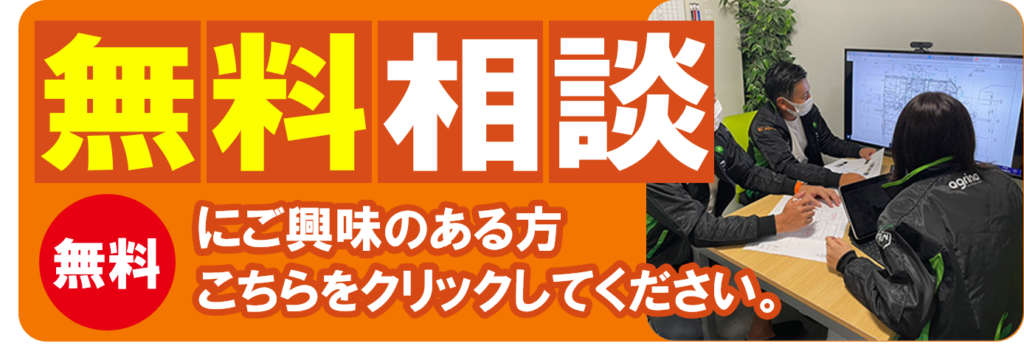NEWS新着情報
2025.10.12スタッフブログ
解体工事で「うるさい!」を防ぐために知っておきたい騒音対策とは【解体工事ブログ】
解体工事で「うるさい!」を防ぐために知っておきたい騒音対策とは【解体工事ブログ】
目次
大阪府大阪市にお住いの皆様こんにちは!
解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事で「うるさい!」を防ぐために知っておきたい騒音対策とは】についてご紹介していきたいと思います。
解体工事はうるさい!

解体工事は重機や破砕作業などを伴う工事のため、「騒音」がもっとも苦情の多い要因の一つです。
「昼間ずっとガガガという音が響く」「話が聞こえない」「寝室で休めない」など、解体工事は近隣住民としては大きなストレスになります。
ここでは、解体工事で騒音が発生する仕組みを正しく知って、具体的な騒音対策、よくあるトラブルとその対応法、そして信頼できる解体業者選びのポイントまで、解体工事の騒音問題について詳しく見ていきたいと思います。
解体工事を安全に、近隣トラブルなく円滑に進めたいとお考えの方の参考にしていただければ幸いです。
読まれています【解体工事に関するトラブル・騒音と振動】の記事はコチラ≫≫
解体工事で騒音が発生する主な理由

解体工事では、建物を安全かつ効率的に壊すために多くの機械や重機での作業、人の作業が必要です。
そして、解体工事で避けられないのが「騒音」です。
では、なぜ解体工事で騒音が発生しやすいのでしょうか。
ここからは、解体工事で騒音が発生する主な原因を詳しく見ていきましょう。
① 重機・機械の使用による騒音

解体工事の現場で最も大きな音が発生するのが、重機や解体用の機械です。
油圧ショベルやコンクリートクラッシャー、ブレーカー、ドリルなどは、コンクリートや鉄骨を破砕する強力な動力を持っています。
そのため、その稼働音や衝撃音は相当な音量になってしまいます。
特に、コンクリートを砕くブレーカーは「ドンドン」「ガガガッ」という打撃音を長時間発生してしまうため、近隣の方にとって最も気になりやすい騒音の一つです。
また、機械のエンジン音や油圧の動作音も継続的に鳴り続けるため、解体工事全体を通して一定の音が発生します。
② 壁や床などの破壊時に発生する衝撃音や打撃音

解体工事では、建物の構造体を取り壊す際に大きな衝撃音が発生します。
特にコンクリート造や鉄骨造の建物では、建物の構造がしっかりしている分、破壊時の「バキッ」「ドンッ」といった音が大きく響きます。
このような衝撃音は一瞬の音でも非常に高い音圧を持つため、周囲の住宅に響きやすく、短時間でも強い不快感を与えてしまうことがあります。
また、廃材を積み上げたり、トラックに積み込む際の落下音も「ガシャン」「ドーン」といった音も断続的に発生します。
③ 地面や建物を伝って響く“低音のうなり”

騒音は「耳で聞こえる音」だけでなく、振動が構造物を通じて伝わることでも発生します。
たとえば、重機の打撃による振動が地面や近隣建物の壁・窓ガラスを揺らすことで、「共鳴音」となって響くというケースがあります。
この共鳴は、建物の構造や地盤の硬さによっても異なり、離れた場所でも「ドンドン」と響く低音として感じられることがあります。
特に木造住宅や窓の多い建物では、音の反射や増幅が起こりやすく、体感的に「音が強くなった」と感じる場合もあります。
④ 車両の走行音や積み込み作業による騒音

解体工事では、建物を壊すだけでなく、廃材を運搬するためのトラックやダンプカーが頻繁に出入りします。
エンジン音、バック時の警告音、鉄製の荷台に廃材を積み込む際の「ガシャーン」という音なども騒音の一因となります。
また、現場の作業員同士の合図や掛け声、指示の声も作業の安全上必要なものですが、住宅街などでは意外と響きやすく、静かな環境とのギャップで気になる方も多いです。
⑤ 周囲に響き渡る反射音・拡散による騒音の広がり

音は空気だけでなく、建物や地面、壁面などに反射・拡散して広がります。
特に都市部や住宅が密集している地域では、隣家の壁や道路のアスファルトに音が反射して「二次的な反響音」として聞こえることがあります。
このように、実際の解体現場から離れた場所でも音が響いて聞こえるのは、音が建物の間を跳ね返って伝わるためです。
そのため、「思ったより遠くからでも聞こえる」と感じることがあります。
法的な基準や規制と守るべき騒音ルール

解体工事には、騒音・振動に関する法的な規制が存在します。
解体工事には、騒音・振動に関する法的を守らないと、行政指導・停止命令などのリスクがあります。
①騒音規制法・振動規制法

解体工事が「特定建設作業」に該当する場合、騒音・振動に関する規制がかかります。
特定建設作業とは、騒音・振動を伴う重機や機械を使用する作業のことを指します。
たとえば、解体作業時間の制限、定められた時間以外の作業禁止、敷地境界での騒音許容値などが法律・条例で定められています。
②区域区分による制限

地域ごとに「第1号区域(主に住宅・学校・病院など静穏が求められる地域)」と「第2号区域(緩やかな地域)」などがあり、作業可能時間や音の許容範囲が変わることがあります。
③社会的に認められる騒音の範囲

法律的には許容されていても、住民が「許容できない」と感じる場合もあります。
これを「受忍限度」の問題と呼びます。
つまり、法律ぎりぎり内でも住民の体感では苦痛と感じられる状況になることがあるということです。
効果的な騒音対策・技術・工法

解体工事で発生する騒音を“完全にゼロ”にすることは現実的には難しいです。
しかし、最新の技術や施工方法を取り入れることで、近隣への影響を大幅に軽減することは可能です。
ここでは、実際の現場で行われている代表的な対策方法を詳しく紹介したいと思います。
① 防音壁・防音パネル・防音シートの設置

解体現場をぐるりと囲むように設置する防音壁や防音パネルは、最も基本的で効果の高い対策のひとつです。
最近では、アルミや鋼製フレームに吸音材を組み込んだ高性能タイプや、軽量で設置しやすい「防音シート」なども使われています。
防音パネルは、金属板の内部にグラスウールなどの吸音材が入っており、音を反射させるだけでなく吸収する効果もあります。
特に住宅密集地や学校・病院が近いエリアでは、防音壁を2重構造にするなど、より徹底した遮音対策が取られることもあります。
読まれています【解体工事における養生シートの役割・養生シートは設置しなくてもよい?】の記事はコチラ≫≫
② 低騒音・低振動型の重機や機器を使用

近年では、騒音や振動を抑える“静音仕様”のモデルが数多く開発されています。
例えば、油圧ショベルやブレーカーなどに防音カバーを取り付けたタイプや、エンジン回転数を自動制御して静かに稼働する重機などがあります。
また、作業中のエンジン回転数を抑制したり、アイドリングストップを徹底したりすることも有効な手段でしょう。
このような細かな工夫によって、作業効率を維持しながらも、近隣への音の影響を最小限に抑えることができます。
③ 手作業による部分的な解体

隣家との距離が近い現場や、構造的に振動が伝わりやすい箇所では、重機を使わず“手作業”で慎重に解体する「手壊し工法」が採用されます。
手壊しは作業時間がかかるものの、打撃音や振動を大幅に減らすことができ、周辺住民への配慮という点では非常に有効な方法です。
④ 作業時間やスケジュールの工夫

解体工事の騒音は「いつ・どの時間帯に発生するか」によって、受け取られ方が大きく変わります。
そのため、早朝や夜間、休日の作業を避けることが基本です。
また、特に音の大きい作業(ブレーカーによるコンクリート破砕など)は、周辺住民が外出している日中に集中して行うといった配慮も大切です。
解体工事前に「いつどんな作業があるか」を近隣住民へ丁寧に説明しておくことで、解体工事への理解を得やすく、トラブル防止にもつながります。
⑤ 騒音・振動の計測と管理

解体現場に騒音計や振動計を設置してリアルタイムにデータを監視することで、異常値が出た場合にすぐに対応できる体制を整える解体業者も増えています。
このような“可視化された管理”は、解体現場の品質向上だけでなく、近隣からの信頼を得る上でも非常に効果的な方法といえるでしょう。
解体工事で起こりやすい騒音トラブルとその対策

解体工事では、どれだけ注意を払っても「音」や「振動」が発生してしまいます。
周辺環境や建物の構造によっては、その影響が想定以上に広がり、近隣トラブルにつながることも少なくありません。
ここからは、実際の解体現場で起こりがちな騒音トラブルと、その際の具体的な対応方法を見ていきましょう。
通行人や近隣住民からの苦情

解体作業時の重機の稼働音や鉄骨・コンクリートを壊す衝撃音が頻繁に発生すると、通行人や近隣住民から「うるさい」「話し声が聞こえない」といった意見が寄せられることがあります。
とくに、住宅地や商店街など人の往来が多いエリアでは、短期間でも強いストレスとなりやすいため、早めの対応が求められます。
屋内環境への影響

騒音レベルが高いと、住民の生活にも直接的な影響を及ぼします。
テレビの音が聞こえない、会話がしづらい、子どもの昼寝や夜間の睡眠が妨げられるなど、生活の質が低下することが原因でクレームが発生します。
「生活妨害」として強く訴えられるケースもあり、迅速な改善が不可欠です。
建物の共鳴・振動被害

重機による打撃振動が建物に伝わると、隣接する住宅の外壁や窓ガラスがビリビリと揺れたり、室内の家具が振動したりすることがあります。
こうした場合、「家が壊れた」「ひびが入った」といった被害申告につながることもあり、施主様にとっても解体業者にとっても大きなトラブル要因となります。
工期停止や作業制限の要求

苦情が繰り返され、住民から強い抗議が出た場合、解体工事を一時中断せざるを得ない状況になるケースもあります。
また、「夜間作業は控えてほしい」「休日は作業しないでほしい」といった時間的制限を求められることもあります。
騒音トラブルへの具体的な対処方法
① 迅速な対応と丁寧な事情説明

まず、騒音トラブルが起こった際に最も重要なのは「スピード」と「誠意」です。
苦情や意見を受けた際は、現場責任者や担当者が直接現場に出向き、相手の話をよく聞いた上で、原因や今後の対策を丁寧に説明します。
放置したり曖昧な対応は不信感を招き、住民の不満がさらに増幅してしまうため、初動対応での誠実さが信頼回復のためにはとても重要です。
② 騒音・振動軽減策の追加

解体現場の状況に応じて、防音パネルや仮囲いの設置強化、散水による粉じん抑制、重機の位置変更や稼働時間の調整など、即効性のある対策をおこないます。
また、騒音や振動の「原因箇所」を特定し、作業方法そのものを見直すことも効果的でしょう。
たとえば、コンクリート破砕機の出力調整や、解体手順の変更によって大幅な改善が見込めるケースもあります。
③ 工事時間の短縮・一時中断の検討

それでも状況が収まらない場合や、苦情が繰り返される場合には、夜間や早朝の作業を控え、特定の時間帯に限定して作業を行うことを検討します。
どうしても必要な作業がある場合は、事前に「〇日〇時から短時間行います」といった説明を行い理解を得るようにします。
一時的な中断は工期に影響するものの、トラブル拡大を防ぐためには大切なので長期的に見て結果的には良い方向に向かうはずです。
大切なのは信頼できる解体業者

解体工事の騒音トラブルは、事前の理解と正しい対策で防ぐことができます。
見積もり段階から「騒音対策」をしっかり確認し、安心して任せられる解体業者を選びましょう。
読まれています【解体業者の選び方 良い業者を見分ける方法のまとめ】の記事はコチラ≫≫
まとめ
今回は、【解体工事で「うるさい!」を防ぐために知っておきたい騒音対策とは】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。


 電話相談
電話相談 メール相談
メール相談 LINE相談
LINE相談
 Twitter
Twitter Instagram
Instagram