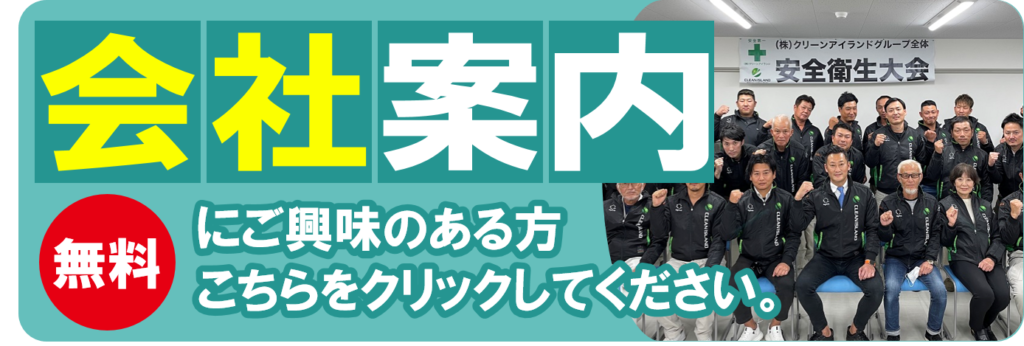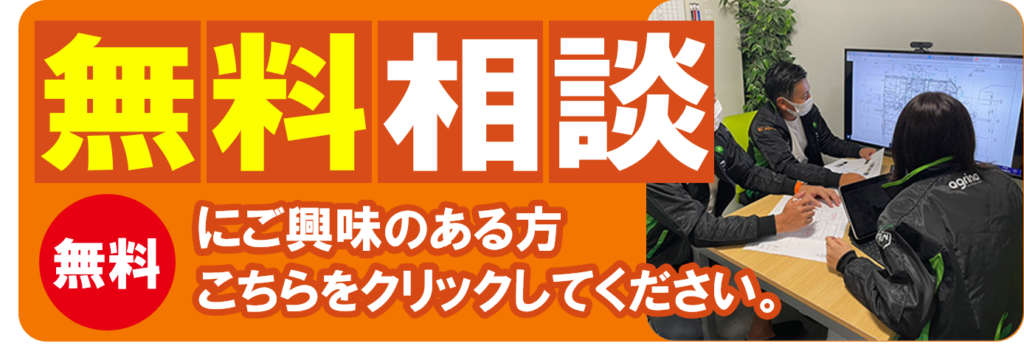NEWS新着情報
2025.9.1スタッフブログ
火事になった家の解体費用と補助金・解体の流れと注意すべきポイント・2025年最新版【解体工事ブログ】
火事になった家の解体費用と補助金・解体の流れと注意すべきポイント・2025年最新版【解体工事ブログ】
目次
奈良県奈良市にお住いの皆様こんにちは!
解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
奈良県の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【火事になった家の解体費用と補助金・解体の流れと注意すべきポイント・2025年最新版】についてご紹介していきたいと思います。
火事になった家は解体すべき?放置のリスク

火災で被害を受けてしまった住宅や建物は、一見すると外観が残っているように見えても、内部の柱や梁、屋根材などが高温にさらされて大きく損傷してしまっているという場合がほとんどです。そのため、耐久性や安全性が著しく低下しており、そのままの状態で居住や再利用することは非常に危険で、実際には困難なケースがほとんどでしょう。
もし、火災後の家屋や建物を放置してしまうと、さまざまなリスクが生じてしまいます。
最も深刻なリスクとしては 「建物の倒壊の危険性」 です。
火災によって木材は炭化し、鉄骨も熱で変形するため、本来の強度を失っています。
そのため、小さな地震や強風でも建物倒壊につながる恐れがあり、居住者はもちろん、近隣住民にも危険を及ぼす可能性があるのです。
次のリスクとしては、「近隣への影響」 です。
焼け残った建材や瓦礫が崩れ落ちたり、雨水が浸入することで害虫や害獣の住処になったり、衛生面でも問題が発生しやすくなります。
また、周辺住民にとっては「火事跡がある」というだけで心理的な不安や不快感を与え、地域環境にも悪影響を及ぼします。
さらに、資産価値の低下 も避けられません。
火災で焼け残った建物がある土地は、不動産市場においてほとんど評価されず、買い手がつかないケースが大半です。
多くの場合、解体工事をして更地にしてから初めて売却が可能となります。
そのため、「建物を残したまま売ろう」と考えても現実的ではなく、むしろ解体工事をして更地にした方がスムーズに売却することができ、資産としての価値も確保できます。
このような理由から、火災で被害を受けた家屋や建物はできるだけ早めに解体工事・撤去をすることが大切でしょう。
安全性の確保はもちろん、近隣トラブルを防ぎ、資産価値を守るためにも、解体工事は重要な選択肢となります。
YouTube解体カズーマチャンネル【火災が遭った現場の解体ってどうしてる!?!?】はコチラ≫≫
火災後の解体が必要となるケース

ある日突然、火災で大切な住まいを失うというのは、想像を絶するほどつらい体験です。
外から見るとまだ家の形が残っていたとしても、実際には火の熱と煙で建物の内部まで深刻な損傷を受けていることが多く、安全に住み続けることは難しいのが現実です。
とくに全焼・半焼で生活ができない状態になってしまった家は、修復よりも解体工事を選ばざるを得ません。
また、壁や屋根が焼け落ち、わずかな衝撃でも倒壊の危険がある建物は、ご自身やご家族の安全を守るためにも早めの判断が必要です。
さらに、役所から交付される「罹災証明書」で「全壊」や「大規模半壊」と判定された場合は、再利用がほぼ不可能となり、解体工事が前提となります。
住み慣れた家を壊す決断は簡単ではありませんが、その後の土地の売却や新しい住まいづくりを考える上で、避けては通れないものでしょう。
火事に遭われた家屋や建物の解体は「過去を消す」ということではなく、「未来に進むための準備」だといえるでしょう。
火事になった家の解体費用相場

火事の後の解体工事は、通常の解体工事よりもどうしても費用がかかりやすいのが現実です。
「ただでさえ火事で大きな損失を受けたのに、さらに解体費用まで…」と、不安に感じられる方も多いのではないでしょうか。
構造ごとの一般的な費用相場は以下の通りです。
木造住宅:1坪あたり 3〜6万円
鉄骨造:1坪あたり 4〜8万円
RC造(鉄筋コンクリート):1坪あたり 5〜9万円
しかし、火災物件の場合はこれに加えて、焼け焦げた廃材を分別・処分するための費用などが必要となるために、そうでない建物の解体工事の費用よりも高くなってしまう傾向にあります。
例えば、火事にあった30坪の木造住宅を解体工事する場合、そうでない建物であれば 100〜150万円 程度で済むケースでも、火災物件では200〜300万円前後 になることも少なくありません。
「思っていた以上に解体工事の費用がかかってしまう…」と感じるかもしれませんが、これは安全性を確保し、焼け残った材質を適切に処理するために必要な費用です。
クリーンアイランドでは、ただ数字を提示するのではなく、お客様の不安に寄り添いながら「どうすれば負担を軽くできるか」を一緒に考えていきたいと思っております。
お気軽にご相談ください。
火事になった家の解体で利用できる補助金・助成制度

火事で損壊してしまった建物を解体する際には、思いがけない出費が大きな負担となります。
そんな時、自治体によっては補助金や助成制度を利用できる場合があります。
火事で損壊してしまった建物を解体する際の直接的な補助金がない場合でも例えば「老朽危険家屋解体補助金」 などを利用することができるケースがあります。
また、神戸市や西宮市をはじめとした一部自治体では、狭い路地に密集する住宅地の安全性向上を目的とした 「密集市街地除却補助」 を設けています。
この制度では、危険な建物の解体工事に対して上限100万〜200万円ほどの補助が出る場合があり、火災物件も条件を満たせば対象となります。
ただし、これらの補助制度は市区町村ごとに内容や対象条件、金額が大きく異なります。
そのため「自分の地域ではどの制度が使えるのか」「火災物件は対象になるのか」を必ず役所の窓口や公式ホームページで確認することをおすすめします。
火災物件の解体は精神的にも経済的にも負担が大きいものですが、公的な制度を上手に活用することで費用の軽減につながります。
少しでも安心して次の一歩を踏み出すために、まずはお住まいの地域で利用可能な補助金制度を調べてみましょう。
火災保険で解体費用はカバーできる?
火災で住まいを失った直後、次に直面するのが「解体費用をどう工面するか」という問題でしょう。
解体工事の費用は大きな出費となるため、多くの方が不安に感じられる部分ではないでしょうか。
実は火災保険に加入している場合、解体工事費用が保険でまかなえるケースがあります。
しかし、補償内容や上限額は保険会社・契約内容によって異なります。
まずは加入している保険会社に相談してみることをおすすめします。
解体前に必ず取得すべき「罹災証明書」
火災後の手続きの中でも、とても重要なのが罹災証明書です。
罹災証明書は、市町村役場が発行する「火災被害の程度を証明する公的な書類」で、解体工事を進める前に必ず取得しておく必要があります。
罹災証明書の主な用途は次のとおりです。
・火災保険の請求に必要
・税金の減免措置を受ける際の根拠資料
・自治体や国の補助金を申請する際の必須書類
罹災証明書の取得の流れは、お住まいの役所(多くの場合は防災課や危機管理課)に申請を行い、現地調査を受けます。
その調査で、建物が「全壊」「半壊」など被害の度合いを判定され、その結果に基づいて証明書が交付されます。
火災直後の混乱の中では「手続きは後でいい」と思ってしまいがちですが、罹災証明書は保険や補助金の申請に欠かせない書類です。
早めに取得しておくことで、その後の手続きがスムーズになります。
あわせて読みたい【火事にあった建物の解体工事はどうする?手続きや費用と解体工事の流れ】の記事はコチラ≫≫
火事になった家を解体する流れ

火災で被害を受けた建物を解体する際には、いくつかの手順が必要です。
通常の解体工事と違い、火災特有の手続きや書類が求められるため、事前に流れを把握しておくことが大切です。
① 罹災証明の取得
まず最初に、市区町村役場で「罹災証明書」を発行してもらいましょう。
罹災証明書は、被害の程度(全壊・半壊・一部損壊など)を証明するもので、火災保険の請求や補助金の申請、税制上の優遇措置を受けるために欠かせない大切なものです。
役所の担当課が現地調査を行い、その結果に基づいて交付されます。
② 解体業者へ見積もり依頼
次に、火災被害を受けた建物の解体を依頼する解体業者を探します。
被災家屋の解体は通常より手間がかかるケースが多いため、複数の解体業者から見積もりを取り、費用や対応内容を比較検討することをおすすめします。
③ 補助金・保険の申請準備
解体工事の費用を軽減するために、補助金制度や火災保険を活用できるか確認しましょう。
補助金は自治体によって条件や金額が異なるため、早めに問い合わせておくことをおすすめします。
また、火災保険を利用する場合には、罹災証明書や写真などの必要書類をそろえて申請します。
④ 解体工事の契約・着工
補助金や保険の申請と並行して、解体業者と正式に契約をします。
契約内容には工期や費用の内訳、廃材処理の方法などが含まれるため、トラブルを避けるためにも詳細な部分までしっかりと確認しておきましょう。
その後、解体工事が始まります。
⑤ 建物解体・廃材処分
実際の解体工事では、焼け残った構造物や瓦礫を撤去し、廃材を適切に処分します。
⑥ 工事完了・建物滅失登記
解体工事が終了したら、建物が存在しなくなったことを法的に証明するため、「建物滅失登記」を法務局に申請します。
これを行わないと、不動産登記簿上には建物が残ったままの状態になるため、土地の売却や再建築の際に支障が出る可能性があります。
建物滅失登記は基本的には1ヶ月以内に行う必要があります。
火事で住まいを失うことは、生活だけでなく心にも大きな負担をもたらします。
ですが、解体の流れや補助金制度をきちんと知っておくことで、その不安を少しずつ軽くすることができるのではないでしょうか。
大切なのは、一人で抱え込まず、信頼できる業者や行政のサポートを上手に活用することです。
火災後の解体工事は、精神的にも経済的にも大きなご負担となることと思います。
だからこそ、私たちクリーンアイランドは単なる解体工事業者としてではなく、再出発を支えるパートナーとして、手続きのご相談から解体までをしっかりとサポートいたします。
安心して、どうぞお気軽にご相談ください。
まとめ
今回は、【火事になった家の解体費用と補助金・解体の流れと注意すべきポイント・2025年最新版】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。


 電話相談
電話相談 メール相談
メール相談 LINE相談
LINE相談
 Twitter
Twitter Instagram
Instagram