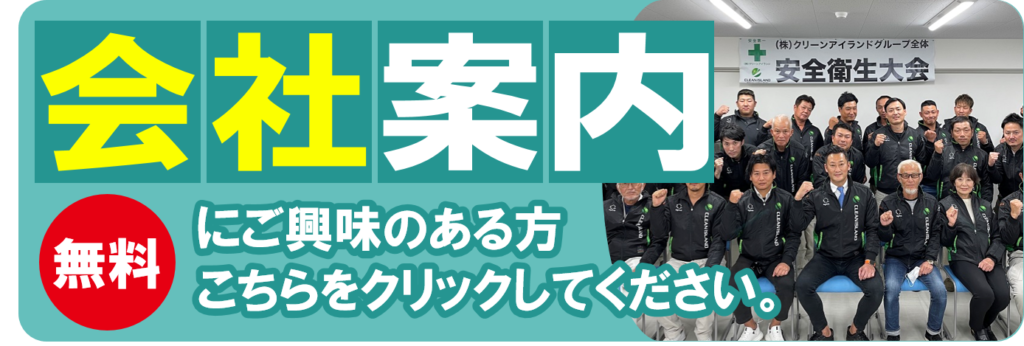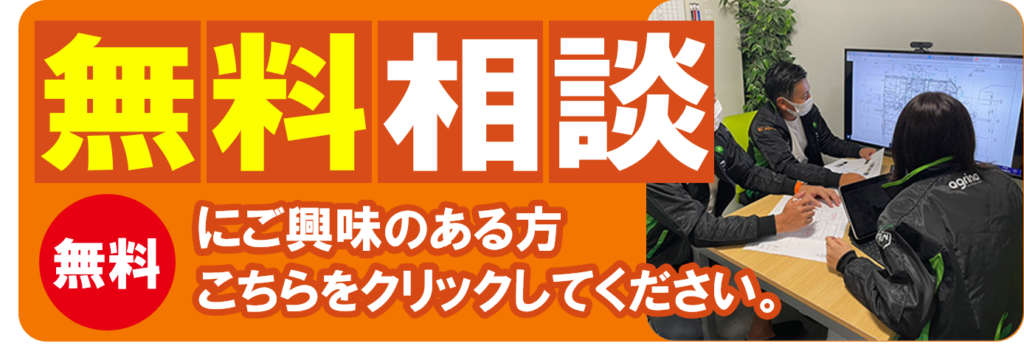NEWS新着情報
2025.10.23スタッフブログ
増え続ける空き家 放置は危険!解体のタイミングと注意点【解体工事ブログ】
増え続ける空き家 放置は危険!解体のタイミングと注意点【解体工事ブログ】
目次
大阪府大阪市にお住いの皆様こんにちは!
解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【増え続ける空き家 放置は危険!解体のタイミングと注意点】についてご紹介していきたいと思います。
空き家の放置

近年、日本全国で空き家が増加しています。
相続や転居などで使われなくなった家が放置されるケースが少なくなく空き家は、ただ存在しているだけでリスクを抱えています。
老朽化による倒壊や火災、不法侵入、害虫の発生など、放置しておくと重大なトラブルにつながることもあります。
ここでは、空き家の解体のタイミングについて見ていきたいと思います。
空き家が増え続ける理由

空き家が増加している背景には、社会的、経済的なさまざまな要因があります。
全国的に見ても、単に「人が住まなくなった家」というだけでなく、長期的な傾向や構造的な問題が絡んでいます。
空き家が増え続ける主な要因3つを見ていきましょう。
①人口減少・少子高齢化

日本全体で少子高齢化が進む中、都市部でも人口減少が進んでいます。
-
若い世代は都市部の利便性の高い場所へ移住することが多く、地方や郊外の住宅に住む人が減少
-
高齢者世帯の減少や死亡により、相続後に住む人がいない住宅が増加
-
結果として使われなくなった住宅が「空き家」として残る
例えば大阪府でも、中心市街地を離れた住宅地では同じ傾向が見られます。特に郊外の一戸建て住宅は、購入希望者が少なく空き家化しやすいというのが現状です。
読まれています【2025年最新版】大阪市で使える解体工事補助金まとめ|申請方法と注意点を徹底解説】の記事はコチラ≫≫
②相続後の管理問題

親や親族の家を相続した場合、次のような問題が起こりやすくなります。
-
相続人が遠方に住んでいて管理できない
-
建物の状態が悪く、リフォームや維持に費用がかかる
-
誰が責任を持って管理するか決まらず、放置される
このように、相続した家をどう活用するかの判断が先送りされると、空き家として長期間残ってしまいます。
例えば、淡路島でも 上記のような理由で空き家が増えています。
③売却・利用の難しさ

空き家を手放したくても、簡単には売れない貸せない場合があります。理由としては以下の通りです。
-
建物が老朽化しており、買い手や借り手がつかない
-
立地が不便でアクセスが悪い
-
土地や建物の権利関係が複雑で売却に手間がかかる
こうした状況では、所有者は「手放すことが難しい」と判断し、結果的に家が放置されることになってしまうのです。
全国の空き家数と空き家率(2023年10月時点)

総住宅数:約6,502万戸(2018年から261万戸増加)
空き家数:約900万戸(前回調査から約51万戸増加)
空き家率:13.8%(過去最高)
空き家が約900万戸、空き家率とともに過去最高の結果となっています。
空き家を放置するリスク

空き家は見た目だけで判断せず、早めに対応することが非常に重要です。
放置すると、さまざまなリスクが積み重なり、所有者だけでなく周囲の住民にも影響を及ぼします。
ここからは空き家を放置することのリスクを4つ見ていきたいと思います。
① 倒壊や事故の危険

木造住宅は築年数が経つと、屋根や柱、基礎部分が劣化し、構造的に脆くなります。
・強風や大雨、地震などの自然災害で倒壊の可能性が高まる
・落下した屋根瓦や外壁の破片で通行人がケガをする事故の危険
・長期間管理されないと、屋根の雨漏りやシロアリ被害が広がり、倒壊リスクをさらに増大させる
「見た目はまだ大丈夫そう」と思っても、空き家の内部は著しく劣化している場合は少なくないのです。
②火災や害虫の発生

空き家は誰も住んでいないため、火災や害虫被害が発生しやすくなります。
・電気設備の劣化による漏電やショートが火災の原因になる
・不法投棄や放火のリスクが高まる
・ネズミやゴキブリ、ハチなどの害虫が繁殖し、周辺に被害を及ぼす
特に住宅密集地では、火災が発生すると隣家への延焼リスクもあるため、周囲への影響が大きくなります。
③近隣トラブル

適切な管理がされず放置された空き家は景観や衛生面に影響を及ぼし、近隣住民とのトラブルの原因になることがあります。
・草木の繁茂やゴミの放置で景観が悪化
・害虫や悪臭により近隣住民から苦情が出る
・空き家周辺で不法侵入や不審者の出入りが発生する可能性
こうしたトラブルは、自治体からの指導や強制撤去の対象となる場合もあります。
④固定資産税や維持費の負担

たとえ誰も住んでいない空き家でも税金や管理費はかかるため、放置しているだけで無駄な出費が続きます。
・固定資産税・都市計画税は居住していなくても課税される
・老朽化した住宅の修繕や防犯対策にかかる費用が増える
・長期間放置すると、解体費用がさらに高額になる
結果として、空き家を長く放置するほど経済的負担が増えるため、早期対応のメリットが大きくなります。
解体すべきタイミングとは

空き家の解体は、「危険が目に見えてから」では遅いケースが多いです。
老朽化が進むほど、解体費用やリスクも増していくため、早めの判断が何よりも大切です。
ここからは、解体を検討すべき具体的なタイミングを紹介したいと思います。
読まれています【空き家の解体工事の際に注意すべき点】の記事はコチラ≫≫
①建物が老朽化して安全に住めない場合

築年数が40年以上経過した木造住宅などは、外見がきれいでも内部が腐食していることが多くあります。
特に次のような兆候が見られたら、解体の検討時期です。
・雨漏りやシロアリ被害が発生している
・壁や床が傾いている、ドアや窓が閉まりにくい
・屋根や外壁の一部が剥がれ落ちている
・地震や台風の際に倒壊する恐れがある
こうした建物を放置すると、近隣への損害 に発展する可能性があり、所有者の責任を問われるケースもあります。
②相続や転居などで今後使う予定がない場合

親から相続した家や、転居後に誰も住まなくなった家は、使わないまま維持費だけがかかってしまう代表例です。
・毎年の固定資産税・火災保険料
・定期的な草刈りや清掃費用
・シロアリ・カビなどの自然劣化
これらを放置していると「特定空き家」として行政から勧告され、税金の優遇措置が解除されることもあります。
早めに売却・更地化・活用などの方針を決めておくことをおすすめします。
③自治体から空き家管理の指導や勧告を受けた場合

「空き家対策特別措置法」により、放置された空き家に対して自治体が指導・勧告・命令を出すことがあります。
特に以下のような状態は危険信号です。
・建物が倒壊・崩落の危険がある
・ごみの放置・悪臭・害虫が発生している
・外観の損傷が著しく景観を損ねている
自治体から勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が外れ、税額が最大6倍になることもあります。
空き家を放置すると、倒壊や火災、近隣トラブルなどのリスクが高まります。
老朽化が進む前に、早めの対応が安心です。
今後使う予定がない家は解体を検討するのも一つの方法でしょう。
まずは専門業者へ相談してみることをおすすめします。
YouTube解体カズーマチャンネル【崩壊!?】昔の空き家には危険が潜んでいる!?長屋の解体現場を視察しにいった結果…】はコチラ≫≫
まとめ
今回は、【増え続ける空き家 放置は危険!解体のタイミングと注意点】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。


 電話相談
電話相談 メール相談
メール相談 LINE相談
LINE相談
 Twitter
Twitter Instagram
Instagram